- 8月 16, 2025
「夜になると咳がひどくなる理由と、その背景にある原因」
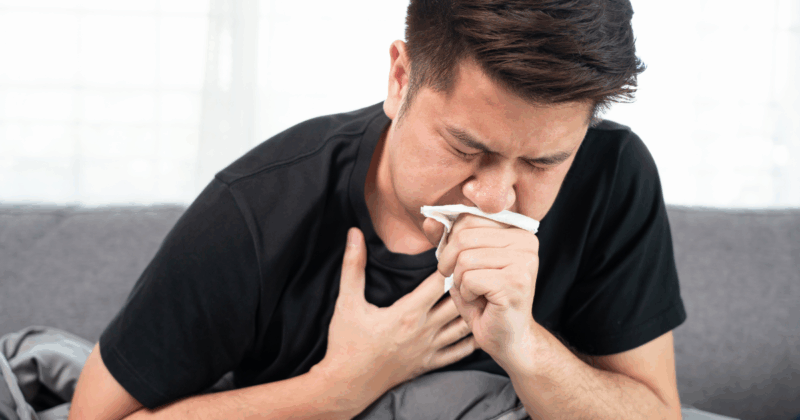
夜の静けさを破る咳——それは原因があります。
外来で患者さんからよくいただく質問のひとつが、「昼間は平気なのに、夜になると咳が出るのはなぜですか?」というものです。たしかに、日中はほとんど気にならないのに、布団に入った途端に咳き込みが始まり、眠れなくなってしまう。やっと眠れたと思っても、明け方に再び咳で目が覚める。こうした症状は数日でもつらいものですが、数週間、数カ月と続けば、疲労や集中力の低下、免疫力の低下など、日常生活や健康全体に深刻な影響を与えます。
咳は単なる“反応”ではなく、体が何らかの異常や刺激を感知しているサインです。
そして、夜間の咳は昼間とは違ったメカニズムが働いています。
夜間に咳が増える背景——体内で何が起きているのか
まず、横になることで気道が物理的に狭くなる現象がおきます。立位や座位では足方向に内臓の重力が向きます。横隔膜がそれに伴い足方向に牽引されることで肺が目一杯に広がり気道が物理的に広がるのです。一方で横になることで内臓による横隔膜の牽引がなくなりその結果、気道の内径が物理的に狭くなり、ちょっとした刺激でも咳が出やすくなるのです。妊娠後期の方はお腹に赤ちゃんがいることで立位でも横隔膜が下に下がらず、肺が物理的に小さくなってしまい咳が出やすくなるのはこのためです。
次に、自律神経の変化が挙げられます。夜は副交感神経が優位になり、気管支が狭くなってしまいます。健康な方では問題にならなくても、喘息・COPDなどの患者さんにとっては咳の引き金になります。
また、寝室の環境も無視できません。乾燥は喉や気道の粘膜を乾かし、防御機能を弱めます。冬は暖房で湿度が下がり、夏はエアコンで気道が冷え、これも刺激となります。寝具やカーペットに潜むハウスダスト、ダニ、カビ、ペットの毛なども夜間の咳を誘発する原因になります。
さらに見落とされがちな原因が消化器からの影響です。逆流性食道炎は、横になると胃酸が食道へ逆流しやすくなり、その酸が喉や気道を刺激します。胸やけや喉の違和感を伴う場合はこの可能性を考える必要があります。食後2時間以内に就寝する生活リズムの方で呑酸症状(口の中が苦い)があり咳が止まらないなどの症状が出たら要注意です。
また、鼻水が喉に流れ込む後鼻漏も、就寝時に咳を誘発する原因になります。
咳の特徴から考えられる主な病気
夜間の咳の背後には、さまざまな疾患が隠れていることがあります。代表的なものを整理すると、
- 喘息:咳に加えて「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった喘鳴が出やすい。季節の変わり目や夜間に悪化しやすい。
- 慢性気管支炎/COPD:痰を伴う咳が数カ月以上続く。喫煙歴のある方に多い。
- 逆流性食道炎:横になると咳が悪化。胸やけや喉の違和感を伴うことが多い。
- アレルギー性鼻炎/後鼻漏:鼻水が喉に流れ込み、就寝中に咳き込みやすくなる。
こうした症状のパターンは診断の参考になりますが、あくまで可能性の一端です。自己判断で長く様子を見てしまうと、治療開始が遅れるリスクがあります。
夜間の咳がもたらす生活への影響
夜の咳は、睡眠不足を招くだけでなく、次のような影響を引き起こします。
- 呼吸器疾患の悪化や慢性化
- 免疫力低下により風邪や感染症にかかりやすくなる
- 集中力や記憶力の低下、仕事や学業のパフォーマンス低下
睡眠は体の回復に欠かせない時間です。咳によって眠りが妨げられる状態が続けば、体調全体に悪影響が及びます。
どんな検査を行うか?
診察ではまず、咳の出る時間帯や頻度、伴う症状、生活環境を丁寧に伺います。そのうえで必要に応じて検査を行います。CT画像検査や採血、呼吸機能検査、呼気一酸化窒素(NO)検査などをうまく組み合わせ適切な診断を行なってまいります。
これらの情報をもとに、原因に合わせた治療を組み立てます。吸入薬や内服薬で炎症や気道収縮を抑える場合もあれば、胃酸を抑える薬やアレルギー治療を優先する場合もあります。
ご自宅でできる工夫
診療と並行して、日常生活で取り入れられる対策も効果的です。
- 室内湿度を50〜60%に保つ(加湿器の活用)
- 枕の高さを調整し、上半身を少し起こして眠る
- 寝る2〜3時間前の飲食や飲酒を控える
- 寝具やカーペットをこまめに掃除し、アレルゲンを減らす
- 季節に応じて寝室の温度・湿度を調整する
これらはあくまで補助的な方法であり、症状が続く場合は必ず医療機関で原因を特定してください。
さいごに
夜間の咳は、呼吸器の病気の大事なサインです。我慢すればそのうち治るだろうと放置してしまうと、症状が慢性化したり、重症化したりすることもあります。長引く咳は肺の悲鳴です。長引く咳は放置せず、早めに呼吸器専門医療機関にご相談ください。
執筆者情報
尾上林太郎(おのうえ りんたろう)
医療法人社団南州会 理事/医学博士
日本呼吸器学会 呼吸器専門医
2013年に聖マリアンナ医科大学卒業後、同大学病院研修医を経て、2015年同大学内科学(呼吸器)大学院入学 呼吸器内科診療助手、2019年同大学院修了 同大学病院呼吸器内科学助教、2024年5月横浜フロントクリニック 院長就任(現職)
【保有資格】
- 医学博士
- 日本内科学会認定内科医
- 日本呼吸器学会呼吸器専門医
- 身体障害者福祉法第15条指定医(呼吸器)
- 難病法における難病指定医(呼吸器)
- 緩和ケア研修会修了医
- アレルギー舌下免疫療法適正使用管理体制に基づく講義の受講・試験の修了医
- オンライン診療研修修了医師
井上 哲兵(いのうえ てっぺい) 医師
医療法人社団南州会 理事長/医学博士
日本呼吸器学会 呼吸器専門医
2009年に聖マリアンナ医科大学医学部を卒業後、同大学の研修医・呼吸器内科を経て、国立病院機構静岡医療センターにて呼吸器診療の研鑽を積む。
2019年4月に医療法人社団南州会 理事長に就任。
同年8月に三浦メディカルクリニックを開院し、以降も以下のクリニックを展開。
- 横浜フロントクリニック(2024年5月開院)
- 東京品川フロントクリニック(2026年1月開院予定)
- 目黒区分院(2026年9月開院予定)
- 新宿区分院(2027年12月開院予定)
【保有資格】
- 医学博士
- 日本内科学会認定内科医
- 日本呼吸器学会 呼吸器専門医
- 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
- 日本医師会認定産業医
- 厚生労働省認定 臨床研修指導医
- 身体障害者福祉法第15条指定医(呼吸器)
- 難病指定医(呼吸器)
- 緩和ケア研修会修了医
