- 10月 4, 2025
喘息の診断にCTは必要? ― 他の病気を排除する大切な検査

はじめに
長引く咳や息切れ、胸の違和感があると「もしかして喘息?」と不安になる方は少なくありません。
しかし実際には、喘息と似た症状を示す病気は肺炎や肺がんなど数多く存在します。
そのため、正確な診断には、可能性のある病気の除外診断 がとても重要です。
そこで役立つのが CT検査。特に当院では、さまざまな呼吸機能検査機器と通常は大学病院などに備えられる80列マルチスライスCT を導入しており、より精度の高い呼吸器疾患の診察が可能です。
当院では、必要と判断されれば、院内で即日検査が可能です。結果も即時、呼吸器内科医が一次読影を行い結果までお伝えしております。また、間違いのない結果を患者様に提供するために放射線科診断専門医(横浜市大及び聖路加国際病院放射線科)による二次読影を行い、精度を高めております。
CTを設置していないクリニックですと、CT検査が必要な場合は総合病院に紹介になったり、後日に画像診断センターで撮影をしたりすることになり、結果が得られるまで最低でも1週間程度、長いと1ヶ月程度かかることがあります。
1. 喘息と似た症状を示す病気
喘息の代表的な症状は、咳・息切れ・呼吸時のゼーゼー音です。
ところが、これらは喘息以外の病気でも見られることがあります。
- 肺炎:発熱や痰を伴うことも多い
- 間質性肺炎:乾いた咳や息切れが主訴
- 肺がん:咳や息苦しさといった症状で自覚することが多い。
- COPD(慢性閉塞性肺疾患):長期の喫煙歴がある方に多い
- 心不全による咳:喘息と誤診されることも多い などなど。
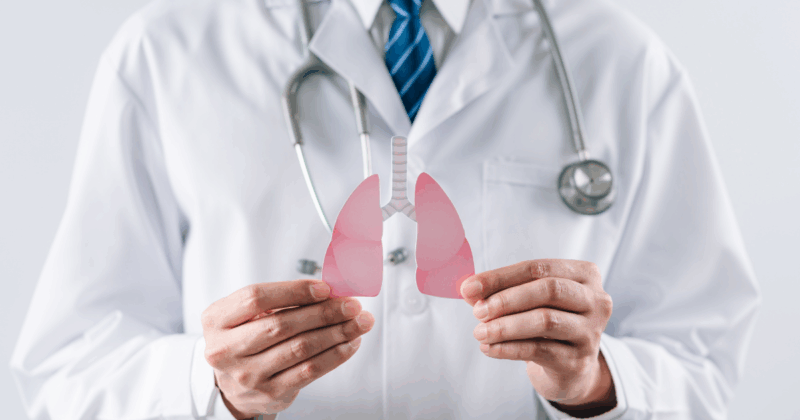
こうした病気と喘息を区別するには、画像検査による確認が必要です。
2. CT検査が有用です― レントゲンとの違い
咳や息切れがあると、まず最初に行われるのが 胸部レントゲン検査 です。
レントゲンは簡便で被ばくも少なく、肺の大まかな状態を把握するのに役立ちます。
しかし、レントゲンには弱点もあります。
- 小さな影や初期の病変は映りにくい
- 気管支や肺の細かい変化までは絶対に確認できない
- 医師によって画像の解釈が異なることがある
そのため、レントゲンによる画像診断で、必要十分な診断ができない場合、
医師の判断で、より精密な検査が必要な場合に選ばれるのがCT検査 です。
CT検査の強み
- 肺の状態を細かく精密に知ることができる
- レントゲンでは分からない小さな影や病変も発見できる
- 肺炎や肺がんなど、喘息以外の病気を高確率で除外できる
つまり、CTは「喘息を直接診断する検査」ではなく、
“喘息と似た症状を示す他の病気を見落とさないために必要になる検査” です。
特に当院では 80列マルチスライスCT を導入しており、低被曝で短時間で高精細な画像を得られるため、
「咳や息切れの原因が本当に喘息なのか」「他の病気が隠れていないか」を明確に判断できます。
3. CT検査に関する疑問(痛み・被ばくなど)
患者さんからよく寄せられる質問が「痛みはあるの?」「放射線は大丈夫?」というものです。
痛みについて
CT検査は体に針を刺したりすることはなく、検査台に横になって数秒間息を止めるだけ。
痛みは全くなく、当院では数分で終わります。また
被ばくについて
放射線の影響を心配される方も多いですが、当院では最新のCT装置を設置しており、被ばく量を抑えて検査ができるように考慮・工夫しております。また常駐の放射線技師が必要最小限の範囲で撮影を行うことで被ばく量をさらに抑えるようにしております。
4. よくある質問(Q&A)
Q1. 喘息の診断に必ずCTは必要ですか?
A. 全員に必要なわけではありません。医師が患者さんの症状経過や身体所見、レントゲン検査や採血の結果などを総合的に判断し、必要があると判断した場合において実施します。CTによる精密検査は「喘息以外の重大な病気が隠れていないか」を確認する上で非常に有効です。症状経過での一つの目安として2週から3週以上咳が続いた場合、重喫煙歴がある場合、他院ですでに治療介入をされているが改善がみられていない場合などはCT検査を考慮すべきです。
Q2. 他のCTと80列CTは何が違うのですか?
A. 80列CTは、一度の息止めで広い範囲を細かく撮影できるため、スピードと精度が大きく向上しています。当院で80列CT検査機を導入した理由は、検査時間が短く済むため呼吸が苦しい方や高齢の方の負担も軽減されるためです。
Q4. 放射線の影響は心配しなくてもいいですか?
A. 最新の低線量技術で被ばく量を抑えているため、必要性がある場合に限り安心して受けていただけます。
Q5. 子どもでも画像検査は受けられますか?どのような場合にCTを含めた画像検査を検討されますか?
A. はい。学童以上であれば症状や必要性に応じてメリットが多いと判断された時に実施することが出来ます。実施にあたり外来担当医が慎重に適応を判断します。小児の場合は、他院で治療を受けたが全く改善の兆しがないとき、重篤な状態が想起される臨床症状が明らかに認められるとき、肺結核など他者への感染が懸念されるときに考慮されます。状況によっては複数の医師が相談の上、適応を判断する事もあります。
執筆者情報
尾上林太郎(おのうえ りんたろう)
医療法人社団南州会 理事/医学博士
日本呼吸器学会 呼吸器専門医
2013年に聖マリアンナ医科大学卒業後、同大学病院研修医を経て、2015年同大学内科学(呼吸器)大学院入学 呼吸器内科診療助手、2019年同大学院修了 同大学病院呼吸器内科学助教、2024年5月横浜フロントクリニック 院長就任(現職)
【保有資格】
- 医学博士
- 日本内科学会認定内科医
- 日本呼吸器学会呼吸器専門医
- 身体障害者福祉法第15条指定医(呼吸器)
- 難病法における難病指定医(呼吸器)
- 緩和ケア研修会修了医
- アレルギー舌下免疫療法適正使用管理体制に基づく講義の受講・試験の修了医
- オンライン診療研修修了医師
井上 哲兵(いのうえ てっぺい) 医師
医療法人社団南州会 フロントクリニックグループ 理事長/医学博士
日本呼吸器学会 呼吸器専門医
2009年に聖マリアンナ医科大学医学部を卒業後、同大学の研修医・呼吸器内科を経て、国立病院機構静岡医療センターにて呼吸器診療の研鑽を積む。
2019年4月に医療法人社団南州会 理事長に就任。
同年8月に三浦メディカルクリニックを開院し、以降も以下のクリニックを展開。
- 横浜フロントクリニック(2024年5月開院)
- 東京品川フロントクリニック(2026年1月5日開院)
- 目黒区分院(2026年9月開院予定)
- 新宿区分院(2027年12月開院予定)
【保有資格・所属学会】
- 医学博士
- 日本内科学会認定内科医
- 日本呼吸器学会 呼吸器専門医
- 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
- 日本医師会認定産業医
- 厚生労働省認定 臨床研修指導医
- 身体障害者福祉法第15条指定医(呼吸器)
- 難病指定医(呼吸器)
- 緩和ケア研修会修了医
執筆者情報
尾上林太郎(おのうえ りんたろう)
医療法人社団南州会 理事/医学博士
日本呼吸器学会 呼吸器専門医
2013年に聖マリアンナ医科大学卒業後、同大学病院研修医を経て、2015年同大学内科学(呼吸器)大学院入学 呼吸器内科診療助手、2019年同大学院修了 同大学病院呼吸器内科学助教、2024年5月横浜フロントクリニック 院長就任(現職)
【保有資格】
- 医学博士
- 日本内科学会認定内科医
- 日本呼吸器学会呼吸器専門医
- 身体障害者福祉法第15条指定医(呼吸器)
- 難病法における難病指定医(呼吸器)
- 緩和ケア研修会修了医
- アレルギー舌下免疫療法適正使用管理体制に基づく講義の受講・試験の修了医
- オンライン診療研修修了医師
井上 哲兵(いのうえ てっぺい) 医師
医療法人社団南州会 フロントクリニックグループ 理事長/医学博士
日本呼吸器学会 呼吸器専門医
2009年に聖マリアンナ医科大学医学部を卒業後、同大学の研修医・呼吸器内科を経て、国立病院機構静岡医療センターにて呼吸器診療の研鑽を積む。
2019年4月に医療法人社団南州会 理事長に就任。
同年8月に三浦メディカルクリニックを開院し、以降も以下のクリニックを展開。
- 横浜フロントクリニック(2024年5月開院)
- 東京品川フロントクリニック(2026年1月5日開院)
- 目黒区分院(2026年9月開院予定)
- 新宿区分院(2027年12月開院予定)
【保有資格・所属学会】
- 医学博士
- 日本内科学会認定内科医
- 日本呼吸器学会 呼吸器専門医
- 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
- 日本医師会認定産業医
- 厚生労働省認定 臨床研修指導医
- 身体障害者福祉法第15条指定医(呼吸器)
- 難病指定医(呼吸器)
- 緩和ケア研修会修了医
